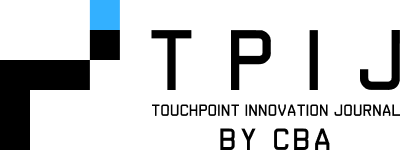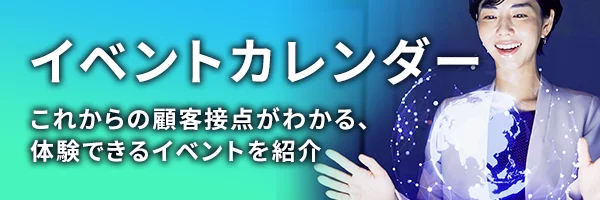生成AIの爆発的普及に伴い、社内でもAI活用大号令が出ているのではないでしょうか。しかし実際には、導入したはずのツールが活用されずに放置されている…そんな声が後を絶ちません。我が社も例外ではない…と思われているかもしれません。
実はその空回り感、あなたの会社だけの問題ではないんです。
ボストンコンサルティンググループの調査によれば、日本の職場におけるAIエージェントの業務導入率はわずか7%と、世界平均の13%と比較して出遅れが目立ち、AI活用が世界の下位に位置しているとのことです。
日本ではAIによる失職の懸念が先行する事態となっています。同社による2024年の調査によれば、日本は生成AIを業務で使用する人の割合が最低であり、生成AIを不安視する割合が非常に高いということが報告されています。また、PwCの調査でも、「(AIが)期待を上回る効果を上げている」という企業の割合は10%となっているとのことです。多くの企業がAI活用の壁に直面している実態が浮き彫りになりました。
なんとも心配性なお国柄が出ている結果となっていますが、なぜこれほどまでにAI活用は進まないのでしょうか?
この問題、コストを削減したいという経営サイドの期待と、仕事が奪われるかもしれないという現場との温度差や、AIそのものに対する誤解が主な原因となっているようです。本当に必要なのは、新たなツールを導入する前に、まず自社のコンタクトセンターが抱える本当の課題をしっかりと見極めることです。
この記事では、AI導入を阻む「5つの神話」を読み解き、現場と経営のすれ違いを乗り越えるための具体的な3つの打ち手を解説します。AI導入を技術の問題ではなく、組織変革の戦略として捉える視点こそが、真のスタートラインです。
海外の最新コールセンターシステムやデジタル・コミュニケーションツールを、19年間にわたり日本市場へローカライズしてきた株式会社コミュニケーション・ビジネス・アヴェニューが解説します。
この記事が解決するお悩み
AIを導入したが活用できていない、効果が出ていない
経営層と現場のAIに対する期待や不安の温度差が大きい
AIに関する過剰な期待や誤解が、導入を妨げている
あなたの組織は大丈夫?AI活用を阻む「5つの神話」

多くの企業がAI導入に対して高い期待を寄せています。とくにコンタクトセンターでは、人手不足に対抗して、なおかつ効率化を図る切り札として導入が進んでいますが、AI活用を進めているすべての企業が期待したような成果を出せているわけではありません。現場で持て余されているケースも少なくありません。
このギャップを生む最大の原因が、AIに対する思い込みや誤解です。これらを「AI神話」と見立てて考えてみるのは興味深い試みと言えるでしょう。なぜこうした神話が生まれるのでしょうか?
その背景には、経営層は「AIでコスト削減」を期待し、現場は「仕事が奪われる」と不安に思うという構図が横たわっています。この期待と不安のギャップがこうした神話、つまりAIへの過剰な期待や誤解を生む流れを生み出してしまっているのです。
この構造から生まれる代表的な5つの「神話」を知り、自社でも無意識のうちにこれらの「神話」を信じ込んでいないか確認してみてください。
神話1:AIは、オペレータの仕事をすべて奪う
非常によく見られる神話です。煽り系のタイトルはPVを稼ぐのに非常に便利な文脈なのでしょうが、鵜呑みにする前にちょっと立ち止まって視点を変えてみましょう。
AIを、人に代わる存在ではなく、人的能力を拡張するチームメイト/パートナーと見るのです。
たとえば、AIが通話内容を自動で要約することで、オペレータが顧客との対話に集中できるなど、人間の価値を引き出す共存の関係を築くことが可能です。AIを単なるツールを超えた、従業員の能力を拡張して、よりクリエイティブな業務へシフトするための戦略的パートナーとして、その価値を社内で浸透させることが必要です。
神話2:AIは、導入すればすぐに成果が出る万能ツールである
即効性(そして完全性も)をAIに期待するのは危険です。
継続的な学習と現場との連携が、AIには必須です。したがって、初期導入後に即効果を求めるのではなく、明確な課題やユースケースに基づき、段階的に精度を高めていく必要があります。
導入初期から完璧な成果を期待・約束するのではなく、特定の課題解決にフォーカスした段階的なロードマップの提示が必要となります。関係者の期待値を適切にコントロールすることが重要です。
神話3:顧客は、AIと対話することを嫌う
顧客満足度が低下する、と思われがちな自動応答。ですが実際には、問い合わせ内容が単純なケースでは迅速かつ正確に対応できるAIが好まれることが多いのも事実です。
問題はAIか?人か?ではなく、顧客のニーズに応じているか、そして適切な役割分担が設定されているかどうかです。顧客の問合せジャーニーを全体的に俯瞰して、AIと人の任せどころ、アサイン先を最適化するチャネル設計の提案が必須です。
神話4:AIは、コストがかかる
確かにかつては、かなりの初期投資が必要になっていたAI。しかし現在では、クラウド型やSaaS型の音声AIサービスも登場しており、スモールスタートが可能になっています。
もうすでに予算の規模でAI導入を諦める時代ではありません。PoCから段階的に進めることで、十分に成果を出すことができます。
SaaSモデルなどを活用した低リスクなPoCを企画・提案することで成果を可視化し、経営からの本格的な投資を引き出すきっかけを生み出せます。
神話5:AIは、導入すればメンテフリーで使える
AIは導入すれば終わり、ではありません。AIは常に学習し、進化していきます。したがって顧客行動や業務フローの変化に応じて継続的に最適化することが求められます。
AI導入を成功させるには、運用チームの関与とデータのフィードバックから成るループ構築が不可欠です。AIを導入するだけでなく、現場からのフィードバックを収集して継続的にAIの性能を改善していくための運用体制を設計・構築する必要があります。
5つの神話を鵜呑みにしたままでは、どれほど優れたツールを導入したとしても、頓挫するネガティブロードマップが見えてしまいます。真に必要なのは、AIという道具を使う前に、自社がどんな問題や課題を解決したいのかを明確にすることです。まずは「AIの真実と向き合い」、自社の課題を見極めることが大切です。
ではこれから「手段」を「目的」にしない戦略的思考法を見ていきましょう。
AI活用における課題解決のための思考法

視点を切り替えましょう。
「AIを導入しなくては!」というツールありきの発想ではなく、「どんな課題を、どう解決するためにAIを使うか」という課題起点の思考を持つことが必要です。
TPIJでも何度か記事化していますが、AIの真実、すなわちAIが得意なことと人間にしかできないことをしっかりと見据えることが大切です。いま一度、AIという存在の持つさまざまな面を現実的な視点から整理してみましょう。
AIが得意なこと:タスク自動化と大量処理
AIの真骨頂は、スピード、一貫性、量、にあります。たとえば以下のような業務は、AIが非常に高い効果を発揮できる領域です。
- 年中無休対応
- 定型的な問合せへの即応
- 通話データやチャットログの自動分析・要約
- 顧客の発話傾向やインテントの傾向分析
- FAQの自動生成・分類
こうした業務は、属人性が低く、ルールや履歴に基づく処理が可能なため、AIベースの業務強化に直結しています。
人間にしかできないこと:感情の理解・サポート、柔軟な対話展開
現時点のAIが逆に不得意なのが、以下のような文脈・感情・関係性が複雑に介在する領域です。
- 顧客の怒りや悲しみに対する共感・対応
- 予測不能なケースでの柔軟な判断、対処、提案
- 企業音価値観・ブランディングを考慮・反映した高度な対話
- ロイヤルティを醸成する感情的なつながりの構築
これらの領域で求められるのは、判断力と解像度の高い感情理解です。この領域をAIだけでカバーするのは不可能です。つまりAIの役割は、こうした人間にしかできない仕事に、人間が集中して打ち込める「環境作り」とも言えます。
たとえばこの理想的な役割分担を成功させた代表例が、Vodafone UKが導入しているチャットボットTOBiです。このAIチャットボットは、月間100万件以上の問い合わせに対応し、そのうちの7割以上を初回対応で完結させています。この成功の裏には、明確な課題設定があったと考えられます。おそらくVodafoneは、応答率の低下や単純な問い合わせによるオペレータ業務の圧迫といった課題を抱えていたのでしょう。そしてその課題を解決する最適な手段として、FAQ対応や手続き案内といった定型的で高頻度な問い合わせをAIに一任できるシステムを構築した、と推察できます。その結果、オペレータは人間でしか対応できない複雑なケースや高付加価値な顧客対応に集中できることになり、運用の効率化とCXの質的改善を両立できた、という流れです。
「AIが何を達成できるのか」という視点から、「どの課題にAIを導入して活用するか」という視点へシフトすることが大切です。つまり、AI活用の目的を、課題ドリブンで考える、ということです。
まずはシンプルに、「今そこにある課題は何か?」を問いましょう。
- 応答率の低下が深刻?
- 顧客満足度が伸び悩み?
- オペレータの離職率が高い?
- SVの業務負担が大きい?
こうした問いかけから、どの業務がボトルネックになっているかを見極め、AIを導入できるか、導入したらどんな改善が見込めるか?を考えることが大切です。その見極めが戦略的思考の第一歩です。
AIは課題解決の手段です。目的では断じてない。ここをはき違えてしまうと、たとえ最新のツールやソリューションを導入したとしても、本質的な成果を得ることは難しくなります。
そうして見えてきた解決すべき課題の先に必要な次のステップが、「社内をどう動かすか」という戦略的アクションです。現場と経営の間という立ち位置から、AI活用の加速に必要な3つの打ち手を見ていきましょう。
「板挟みから脱却せよ」―現場と経営の壁を超える3つの打ち手

AI活用の目的が明確化しても、次にそれを社内で実際に動かしていくのはまた別の話になります。別の話というより、むしろ、別の難題といった方が良いかもしれません。
優れたツールを選定して課題と活用シーンを整理したとて、組織が動かなければ無意味です。プロジェクトは頓挫します。
組織が動かないことの背景には、「AI活用」に対して、社内の期待と不安が対立している構造が見え隠れします。つまり、経営層には「AIでコスト削減」「業務効率化」「数字を出してくれ」という成果に対する期待がある一方で、現場には「AIで仕事が奪われるのでは?」「今の業務を否定されたくない」という抵抗があるわけです。
この期待と不安のギャップが組織が抱える壁の正体です。
現場の壁:AI活用による変化が、自分たちの役割の消失や熟練の経験の軽視につながるのでは?という心理的不安。とくにオペレータやSVの現場には、今のやり方で十分という暗黙の前提が強く根付きがち。
経営の壁:「とにかく成果を!」「投資対効果を見せろ」といった圧力。現場との温度差を無視したまま導入を急がせるケースも存在する。
この板挟みの中間にいるIT部門や情シスの管理職は、現場の声もわかりますし、経営の論理も理解している部分もあるため、変革の推進役としてキーパーソンになり得る存在です。
McKinsey & Company の提言でも、企業がAI活用を成功に導くには「戦略」「人材」「AI基盤」の3つを「連動させる」必要があるとされており、その調整・実行役としてそうした部門の管理職によるリーダーシップが不可欠となります。
そしてこの組織の壁を越えて、AI活用の現実解を導き出すための3つの打ち手がこちらです。
打ち手1:現場の壁を越える
現場が抱える「AIに仕事を奪われる」という漠然とした不安に対して、導入の目的と目標を共有して、このプロジェクトをやることの理由と意義を丁寧に可視化することが欠かせません。ワークショップ形式で課題の洗い出しから参加してもらって、一緒に作る感覚を生み出すことが現場との信頼関係の構築につながっていきます。
打ち手2:経営の壁を越える
経営は「早くROIを!」と急かすものの、AIは導入すれば即成果が出るものではありません。だからこそPoCなどで小さく始める、いわゆるスモールスタートを実施して、小さくても確かな成功事例を作ることが重要です。その成果を、経営が重視するKPI(コスト削減率や応答時間の短縮など)に落とし込み、わかりやすい価値として報告することで、次の予算獲得やスケール拡大への道が広がっていきます。
打ち手3:双方の壁を越える
AIを入れて終了!ではありません。人間の役割を変化させていくこと、そして組織の未来像を明示することが欠かせません。AIに定型業務を任せることで、「オペレータは顧客との関係性を深める仕事に専念できるようになる!」という希望にあふれたストーリーを見せること、そして必要となるAIスキルやスキル習得後のキャリアの方向性を提示することが大切です。
こうした打ち手に基づいたさまざまな働きかけにより、現場も経営も納得できる「人とAIの協働」というイメージが共有されていくのです。またこうした打ち手は、単なるAI導入プロジェクトに対する戦術ではありません。現場の意識を変えて、経営の理解を得て、組織全体をアップデートしていく「組織変革プロジェクト」そのものであると言えます。それこそ必要な視点なのです。
最後に:AI活用は「技術プロジェクト」ではなく「組織変革プロジェクト」である
AI導入はもはや技術の選定や、プロダクト導入だけでは語れません。そのフェーズは過ぎ去っています。
AI活用はなぜ進まないのか? AIにありがちな神話や誤解、AIの本質的な真実の部分を見極める視点・思考法を持つことの大切さ、そしてその思考を阻む組織的な壁という視点からその背景をひもときました。したがって目指すべくは、課題ドリブンの組織変革戦略です。
AIを使うのか使わないのか、何のAIを導入するのか、ではなくて、「自分たちの組織は何のためにAIを使うべきなのか?」という問いから始める必要があります。そこからスタートしない限り、本当の意味での成果にはつながりません。つまり、AIは目的ではなく「ビジネス課題を解決するための設計要素」なのです。そう考えることが必要な時代になっているのです。
そのために必要なのは、課題解決と変革という視点です。したがって今カスタマーサービスに求められているのは、課題を見極め、その解決策を戦略的に設計する力です。その過程において、AIは初めて生きたソリューションとなります。
「自社(のコンタクトセンター)が解決すべき課題は何か」―この問いをぜひ考えてみてください。そして、この問いを投げかける対話のハブになることこそ、現場と経営の間に立つ管理者の重要な役割です。まずは雑談から始められるかもしれません。その会話がまさに、AI導入の本当のスタートラインになるかもしれないのです。それこそが、単なるツール導入ではなく、解像度の高い未来像を描いて実際に実現するための、戦略的AI活用への第一歩となっていくことでしょう。